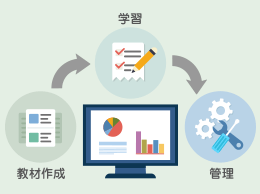「人手不足」「研修時間が取れない」――そんな切実な声が上がる保育業界の“常識”を変える研修サービスとして注目を集めるのが、学研グループの『学研せんせいサポートHOINQ(ほいんく)』です。2025年4月のリリースからわずか1ヶ月半で80施設・2,800名が利用。15分という短時間で保育の現場に大きな変化をもたらしています。保育業界の課題に寄り添い、解決を目指す『HOINQ』の特長と成果とは? 担当の和田様にお話を伺いました。

管理部 経営管理課/マーケティング戦略室
和田 健 様
導入前の課題
- 保育現場の課題を解決するオンライン研修を、ゼロから短期で立ち上げたい
- 保育の現場でも使いやすいシステムが必要
導入サービス
- KnowledgeDeliver、カスタマイズ、DKクラウド
導入後の成果
- 園内研修サービス『HOINQ』の立ち上げをシステム面から支援し、短期間での運用開始を実現
- リリースから約1ヶ月半で80施設・約2,800名の保育者が利用
- 職員間の対話促進や保育理念の浸透により、園全体のチーム力向上に寄与している
- 今後はコンテンツのさらなる拡充とサービスの利用促進により、“保育の質” 向上を目指す
園内研修が“できない”時代へ。深刻化する保育現場の課題
はじめに、保育業界の現状についてお聞かせください。どういった課題があるのでしょうか。
和田様:保育業界は他の業界に比べて離職率が高く、人材不足が深刻です。離職理由は待遇面に加え、人間関係の悩みも多く、その背景には日常業務の忙しさによる職員間のコミュニケーション不足が挙げられます。 保育者同士で “経験”や“思い”を共有する機会がなく、孤立感やチーム力の低下につながっています。
もうひとつの課題は、少子化による園児の減少です。とくに郊外では、子どもの数に対して保育施設が多く、経営難に陥る園も少なくありません。かつては待機児童対策として“保育の量”が重視されてきましたが、今は“保育の質”が重視される時代になってきました。保護者も「近さ」だけでなく、「安心して預けられるか」「保育方針に共感できるか」という視点で園を選ぶ傾向が強まっています。
なるほど。そういった状況に対し、保育現場ではどのような対応がなされていますか?
和田様:本来であれば、園内研修を通じてこうした課題にアプローチするのが効果的です。ですが、現実には研修の時間を確保することすら難しくなっています。「いかに研修を実施するか」自体が新たな課題になっているのです。
学研グループの中で保育園・幼稚園・認定こども園向けの事業を展開する私たちGakken SEEDとしては、保育現場が直面する課題を何とか解決したいという強い思いから、今回『学研せんせいサポート HOINQ(ほいんく)』を立ち上げました。
「うちの保育方針って何だっけ?」――“理念”と“実践”をつなぐ『HOINQ』の仕掛け
新しい園内研修サービス『HOINQ』の概要を教えてください。
和田様:1回15分で完結する、保育者向けのオンライン研修サービスです。現場で起こりがちな「保育あるある」の事例をテーマにしたコンテンツで、すぐに実践に活かせる内容になっています。特別な機材は必要なく、パソコンやタブレットなど、インターネットにつながる端末があればすぐに導入いただけます。
保育現場の課題にどのように応えているのでしょうか?
和田様:短時間で実施できるため、忙しい保育現場でも取り組みやすい設計になっています。また、最大の特長は“グループワーク”です。これまでの一方向的な研修とは違い、保育者同士が “経験”や“思い”を自然に共有し合える場を提供することで「対話を通して学び合う」サービスとなっています。
主な研修の流れを教えてください。
和田様:1回の研修は次の4つのステップで構成されています。
- 導入動画(2分):保育の現場で起こりがちな事例を提示
- 個人で考える時間:「自分ならどう対応するか」「これまでどうしていたか」を整理
- 監修の先生 による解説:よりよい対応や視点を分かりやすく解説
- グループワーク(5分):専用のワークシートを用いて、保育者同士で意見交換・共有
※ワーク形式のほか、講義形式のコンテンツも配信
グループワークで使用するワークシートに「園の保育方針」を記入する欄があるそうですが、それはなぜですか?
和田様:保育理念と日々の実践をつなげるための重要な仕掛けです。毎回ワークシートに園の保育方針を記入することで、保育者1人ひとりが、理念を意識しながら研修テーマに向き合えるようになります。その結果、子どもや保護者に対する対応にも、自然と園の方針が反映されるようになります。
つまり『HOINQ』は、園の理念に根差した保育の実践を実現するための、重要な役割を果たしているということですね。
和田様:はい。実際に導入園の中には 、ワークシートを前に「うちの園の保育方針って何だっけ?」と立ち止まる先生が少なくありませんでした。これは、理念が形骸化していた表れであり、この問いをきっかけに対話が生まれること自体が大きな価値となります。こういった仕組みは従来の研修サービスにはなく、導入した園からとても喜ばれています。
デジタルサービスでありながら、紙のワークシートを採用されたのはなぜですか?
和田様:デジタルに不慣れな先生でも取り組みやすいよう、あえて手書きを採用しました。これは、研修への心理的なハードルを下げるうえでも効果的でした。
先生の主語が“私”から“私たち”へ――現場に生まれたチームの連帯感
『HOINQ』を導入された園から、どんな反応が届いていますか?
和田様:一番うれしかったのは、「先生たちの主語が“私”から“私たち”に変わりました」という声をいただいたことです。これは職員間のコミュニケーションが深まり、チームとしての連帯感が醸成されてきている証拠だと感じています。
具体的にはどのような変化があったのでしょうか?
和田様:導入当初は、グループワークに30分近くかかってしまう園もありました。ですが、継続するうちに園内で保育観が共有・統一されていき、最近では5分で完了するようになったという、目に見える成果も報告いただいています。
職員間のコミュニケーションにも変化はありましたか?
和田様:保育現場では、とくに若い保育者がベテランに意見を言いづらいという課題があります。『HOINQ』のグループワークは、あくまでも『研修テーマ』に対して「私はこう思います」と発言できる場になっているため、立場に関係なく対話できる環境が自然に生まれ、世代間のギャップを埋めるきっかけにもなると好評です。
研修時間の確保が課題ということでしたが、『HOINQ』はどのようなタイミングで利用されているのでしょうか。
和田様:多くの園では、「15分ならできる」ということで、午睡中や降園後の時間帯に利用されています。「15分すら難しい」という園では、導入動画や解説は個人で見て、最後の5分だけ集まってグループワークをされています。こうした柔軟性も、『HOINQ』が現場に受け入れられている要因だと思います。

現場の“保育あるある”をテーマにした実践的なコンテンツを配信。研修準備の必要が無くなり、担当者の負担軽減にもつながっている
リリース1ヶ月半で利用者2,800名を突破!即決採用した“システムの強み”
すでに多くの園で導入が進んでいると伺いました。
和田様:おかげさまで、現在80施設で導入され、予約を含めると130施設にまで広がっています。サービス開始から約1ヶ月半で2,800名もの先生方に利用いただいていることに、大きな手応えを感じています。『HOINQ』の設計や思想が現場ニーズとマッチしていたこと、そしてそれを支えるシステムの使いやすさも大きかったと思います。
システムには弊社のLMS「KnowledgeDeliver」を採用いただきましたが、どのような経緯でしたか?
和田様:学研グループの学研メディカルサポートがすでにKnowledgeDeliverを導入していた実績があり、「このシステムならうまくいくから」と勧められたのがきっかけです。弊社会長の五郎丸も太鼓判を押すシステムであったため、実際に操作してみたところ、直感で操作できるわかりやすいUIに驚き、ほぼ即決で導入を決めました。これならデジタルに不慣れな方 でもすぐに使いこなせるだろうと感じましたし、実際に導入時の混乱もほとんどなく、現場の先生方からも「使いやすい」と評判です。

スケジュール的にはかなりタイトだったと聞いていますが。
和田様:プロジェクトの担当を引き継いだのが年明けだったので、4月のリリースまで本当に時間がなくて。最初はかなり不安でしたが、デジタル・ナレッジさんがとても親身にサポートしてくださり、実質1ヶ月半ほどの短期間で、保育の現場にフィットする形に仕上げることができました。このスピード感も、導入拡大の追い風になったと思います。
“保育の質”向上を目指して。保育業界全体へ広がるインパクト
『HOINQ』が広がることで、保育業界全体にはどのような変化が期待できますか?
和田様:少子化が進む今、求められているのは“子ども主体”の質の高い保育です。『HOINQ』はその実現に確実に貢献できると考えています。
『HOINQ』を通じて園の理念が浸透し、職員の資質とチーム力がアップすれば、保育者はより自信と誇りを持って子どもたちに接することができるようになりますし、保護者も安心して子どもを預けることができるようになります。そして、子どもたちにとっては、どの先生からも一貫した保育を受けられることで、安心して過ごせる環境が整います。
保護者の皆さんからはどのような声がありますか?
和田様:近年はパート職員の保育者も増えていますが、保護者の方から「パートの先生も研修を受けているんですか?」と聞かれることがあります。『HOINQ』は園の全職員にIDを発行し、同一研修を受けられる仕組みのため、保育の一貫性を保つうえで非常に効果的ですし、結果として、働きやすさの向上や離職率の低下にもつながると期待しています。
「地域で一番選ばれ続ける園」になる――保育業界と二人三脚で目指す未来
『HOINQ』は学研グループの中でどういった意味をもつサービスでしょうか。
和田様:『HOINQ』は、学研グループ内でも戦略的な主力商品として位置づけられています。長年蓄積してきた保育に関する豊富なノウハウを活かし、従来の“モノ”中心の提供から、研修など“形のないサービス”へと展開する取り組みの主軸を担っています。『HOINQ』をきっかけに他サービスの導入へつながる事例も増えており、今後は、『HOINQ』を通じて保育現場との関係性が深まり、より近い立場で多面的な課題へアプローチできる可能性が期待されています。
今後の抱負をお聞かせください。
和田様:Gakken SEEDは、「地域で一番選ばれ続ける園」づくりを全国の保育施設と共に進めていきます。『HOINQ』のコンテンツの拡充に注力すると同時に、来期末までに2,000施設 での導入を目標に掲げ、より多くの現場に『HOINQ』を届けていく方針です。
機能面では、どのようなことを検討されていますか?
和田様:受講状況・成長の“見える化”や、他園がどのように研修を活用しているかがわかる機能があれば、研修価値をより高めることができるのではと考えています。たとえば、「同じ研修を受けたA園の先生はこんな感想を持っています」といったフィードバックがあると、新たな気づきやモチベーション向上につながります。
可視化の手段としてはデジタルバッジが有効です。受講証明だけでなく、個人のスキルや経験も可視化でき、受講促進や評価、指導にも活用できます。
和田様:とても興味があります。実際に「修了証を発行したい」という園もありますので、前向きに検討していきます。
保育者は命を預かる大切な仕事。それを支える取り組みはとても意義深いと感じました。
和田様:Gakken SEEDのミッションは「すべての子どもたちの笑顔のために」。そのためには、何よりもまず、保育者の皆さんが安心して働ける環境が必要不可欠です。これからもデジタル・ナレッジさんと連携し、現場の声に真摯に耳を傾けながら、価値あるサービスを届けていきたいと思います。
【デジタル・ナレッジからみた本事例のポイント】
今回、改めてサービス化の経緯をお聞きし、保育業界の課題感や、保育の量から質へ、という大きな転換期であることを再認識し、さらに身の引き締まる思いです。
Gakken SEED様の有するノウハウ・コンテンツをスムーズにシステム化することができたことが、そういった「意識の転換期」のニーズに適応でき、1ヶ月半で利用者2,800名を突破する結果につながったのではないかと考えております。
このような意義の大きなサービスに携われておりますことをとても誇らしく思います。
今後も、より価値あるサービスの実現を目指し、Gakken SEED様と足並みをそろえ、また時には率直な意見を交わしながら、パートナーとしてご支援をさせて頂きたいと考えております。
≪株式会社デジタル・ナレッジ ソリューションパートナー事業部 コーディネータ リーダー 荒井 研祐≫
ご利用いただいた製品・サービス
- カスタマイズ
- DKクラウド
お客様のサイト
お客様情報
| 名称 | 株式会社Gakken SEED(Gakken SEED Co., Ltd.) |
|---|---|
| 設立 | 2006年(平成18年)11月1日(2024年(令和6年)10月1日商号変更) |
| 本社所在地 | 東京都品川区西五反田二丁目11番8号 |